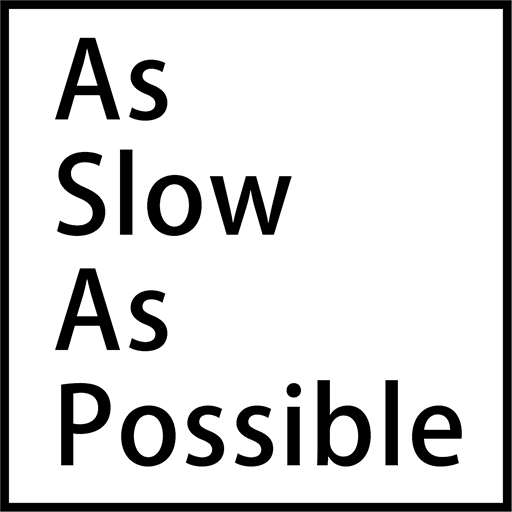お米を考える本 井上ひさし(選)
- 2025.09.07
- 本

水戸納豆がピンチという衝撃的なニュースを新聞で見た。藁に包まれた「わら納豆」の生産ができず販売を一時中止するということである。なぜこのニュースが衝撃的なのかと言うと、「わら納豆」は、その納豆を包んでいる「わら」を使えば自宅で納豆を作ることができるという、二度美味しい商品だからである。茨城県を訪れた際に、わら納豆を買って帰ったのであるが、これは出来上がった納豆を藁に包んだだけの商品なのか、本当に納豆菌の付いた藁で作った納豆なのか、どちらなのだろうと思った。そこで、その藁を使って自分で納豆を作ってみることにした。茹でた大豆をその藁で包み、三日ほど発砲スチロールの容器で保温してみると、なんと見事に糸を引いて粘る納豆に変化したのである。その素晴らしい「わら納豆」の販売が中止になる。理由は藁不足であるとのこと。稲作の機械化が進み、コンバインで藁が切り刻まれてしまい、納豆を包むことができるような長い藁は手に入らないらしい。これまで手作業で収穫をしてもらって、なんとか長い藁を手に入れていたのだけれど、農業の生産合理化のため手作業を継続してくれる農家さんがどんどんと減っているということが背景にあるとのことだ。
米の価格が高くなり、選挙の争点にもなる大きな国の問題となっている。お米を食べること、お米を作ること、とはいったいどういう意味があるのか。この本は、お米が日本人の主食であることはもちろん、日本でお米がつくられ日本人がお米を食べ続けてきたことは必然かつ合理的であること、お米つくりが国土や地域をつくるための重要な位置づけであること、お米つくりは産業ではなく文化であること、お米をつくることで環境や安全を守り続けてきたこと、そういったお米とお米にまつわる様々なことを教えてくれる。お米が高い高いと嘆く前に、私たち日本人はお米のことをもっともっと深く知る必要がある。そして果たして私たちは将来も、わら納豆を食べることができるのだろうか?
本: 「お米を考える本」 井上ひさし(選)
ブックカバー: 元祖天狗納豆
-
前の記事
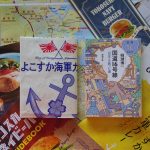
国道16号線 「日本」を創った道 柳瀬博一 2025.08.24
-
次の記事

蛍と月の真ん中で 河邉 徹 2025.10.19